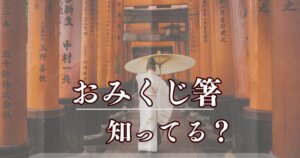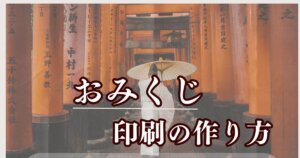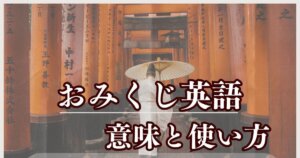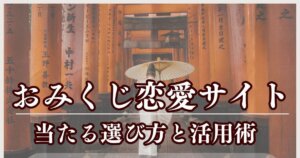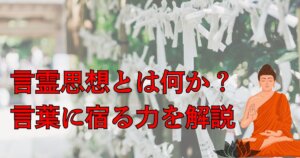日本は四方を海に囲まれた海洋国です。そんな日本では、古来から海に対する畏敬や感謝が深く、神話の世界にも「海の神」が何柱も登場します。
本記事では、「日本 神話 海 の 神」というキーワードをメインに、日本神話で語られる海の神様の正体や名前、ワタツミとの関係、さらには海の女神の存在や海神を祀る神社などについて詳しく紹介していきます。
この記事を読むと分かること👇
海の神様「ワタツミ」や「スサノオ」の役割と由来 海の女神・豊玉毘売命や弁財天の意味 日本神話における海の神三神とは? 海の神を祀る全国の代表的な神社の紹介
日本神話で海の神は誰ですか?
日本の神話で水の神様は誰ですか?
日本神話で「水の神」とされる例はいくつかありますが、その中でも特に「海を司る神」として知られるのがワタツミ(綿津見神)です。
また、「スサノオ(建速須佐之男命)」を海神とみなす解釈も存在します。スサノオは“海原を統べる”神として生まれたとされる一説があるため、「海の神」の側面を持つとされます。
しかし、純粋に「海」だけを支配する神として最も代表的なのは、ワタツミ(わたつみ/わだつみ)や、その別名・派生形とされる住吉三神(すみよしさんしん)などが挙げられます。
また、一部文献では「豊玉彦(とよたまひこ)」の名で海神が表れたり、地方の伝承には海を司る神が無数に存在したりします。
海の神の名前は?「ワタツミ」とは海の神のこと?
「ワタツミ」とは海の神のこと?
結論を言えば、「ワタツミ」は日本神話における“海の神”を指す総称でもあり、個別の神名でもあります。
- 「ワタ(海)+ツ(の)+ミ(神霊)」という語源説が有力で、「海の神霊」という意味をもつのがワタツミという名の成り立ちといわれています。
- 実際には『古事記』などに「大綿津見神(おおわたつみのかみ)」や「底津綿津見神」「中津綿津見神」「上津綿津見神」という三柱の神が登場するなど、ワタツミの名を持つ神は複数存在します。
こうした背景から、ワタツミを海神全般のイメージとして捉え、「海の神=ワタツミ」と漠然と理解されることも多いです。
古来、日本の海人(あま)の氏族や漁民から信仰を集め、航海安全や豊漁、海上交通の守護神として崇敬されてきました。
海の神三神とは?
日本神話には「海の三神」と呼ばれる組み合わせがいくつか挙げられますが、代表的なのは次の二例が有名です。
- 底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)・中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)・上津綿津見神(うわつわたつみのかみ)
- 『古事記』で、イザナギが黄泉国から戻って海で禊(みそぎ)をしたときに生まれたという三柱のワタツミ神。
- 底・中・上と海の水深の違いを表しているとされ、海域の構造を象徴する神々ともいわれる。
- 住吉三神(すみよしさんしん)
- 『日本書紀』で「イザナギの禊ぎ」の際に生まれた三柱の神。いわゆる住吉大神として、航海安全・海上守護の神として著名です。
- 厳密に言うと名前に「ワタツミ」が入ってはいませんが、海に深く関わる三神ということで、海の神三神とされることがあります。
ただし「海の神三神」というフレーズ自体が何か一つに定義されているわけではないため、文献や地域で解釈が異なる点に注意が必要です。
日本神話 海の女神は誰?海の神 一覧
海の女神は誰?
日本神話における“海の女神”として最も知られるのは豊玉毘売(とよたまひめ)です。
- 彼女は、海神の娘として海底宮に住み、山幸彦(火遠理命)と結婚した後、出産のシーンで“鰐(サメ)の正体”を見られてしまい、海宮へ戻った、という神話が有名です。
- いわば「ワタツミの娘」として登場し、海の王女的なイメージを持つ女神です。
また、別の角度からは、「弁財天(市杵島姫命)」を海の女神と捉える例もあります。これは、日本古来というより、ヒンドゥー教の水神サラスヴァティー(Saraswati)が日本に伝わって弁財天と同一視されたため、「水辺や海とも縁が深い」とする信仰があるのです。ただし、神道の範疇に入るかは微妙な面があります。
海の神様 一覧(日本)主要な神々とその役割
| 神名 | 読み方 | 種別 | 主な役割・特徴 |
|---|---|---|---|
| 大綿津見神 | おおわたつみのかみ | 男神 | 海そのものを司る神。海神の総称「ワタツミ」の中心的存在 |
| 底津綿津見神 | そこつわたつみのかみ | 男神 | 海の最深部を司る神 |
| 中津綿津見神 | なかつわたつみのかみ | 男神 | 海の中層を司る神 |
| 上津綿津見神 | うわつわたつみのかみ | 男神 | 海の表層を司る神 |
| 住吉三神 | すみよしさんしん | 男神 | 航海安全・海上交通の守護神。住吉大社に祀られる |
| スサノオ命 | すさのおのみこと | 男神 | 海原を統べる神としての側面を持つ。荒ぶる海との関係も |
| 豊玉毘売命 | とよたまひめのみこと | 女神 | 海神の娘。海の女神であり、皇室の祖先とされる存在 |
| 玉依毘売命 | たまよりひめのみこと | 女神 | 豊玉毘売の妹。神武天皇の母で、海と縁の深い女神 |
| 市杵島姫命 | いちきしまひめのみこと | 女神 | 宗像三女神の一柱。弁財天と習合、水辺の守護神 |
| 湍津姫命 | たぎつひめのみこと | 女神 | 宗像三女神の一柱。急流や航海安全の神格を持つ |
| 田心姫命 | たごりひめのみこと | 女神 | 宗像三女神の一柱。海・川の境界を象徴する存在 |
他にも海や水と関係の深い信仰の神々(日本神話以外)
補足表|海と関わる信仰の神々(番外編)
| 神名 | 読み方 | 起源・系統 | 主な役割・補足 |
|---|---|---|---|
| 弁財天 | べんざいてん | 仏教由来(サラスヴァティー) | 水・音楽・財運の女神。市杵島姫命と習合されることもあり、海辺の神社にも多く祀られる |
| 宇賀神(宇賀弁財天) | うがじん/うがべんざいてん | 農業神・民間信仰 | 穀物神として信仰されていたが、弁財天と融合し、財福・水神としての信仰も |
| 豊玉彦命 | とよたまひこのみこと | 日本神話 | 豊玉毘売命の父とされる海神。ただし神話内での登場は少ない |
| 海童神 | わだつみのこがみ | 地方伝承 | 九州などに残る海の若神。正史に記述はないが、漁民の間で信仰されている |
補足解説文
上記の神々は、いずれも「海・水・航海」などと深く関わる存在として信仰されてきましたが、今回の主表とは分けて紹介しています。理由は以下の通りです。
- 弁財天や宇賀神などは、仏教や民間信仰が起源で、厳密には日本神話には登場しません
- 豊玉彦命や海童神は登場回数や史料が少なく、詳細な神格が定まっていないためです
それでも、地域ごとの信仰や神社では「海の神様」として大切に祀られていることも多く、関心のある方はぜひ各神社での由緒も調べてみてください。
日本神話 海の神様 |わたつみの神 神社
大綿津見神 神社・海の神様 名前
「わたつみの神」を祭る代表的な神社を挙げてみましょう。
- 住吉大社(大阪府)
- 住吉三神(底筒之男命・中筒之男命・上筒之男命)を祀る。古代から海上交通の安全祈願で著名。
- 宗像大社(福岡県)
- 三女神(市杵島姫命・湍津姫命・田心姫命)を祀るが、海神との関係も深く、航海安全や道主貴(どうしゅのむち)神など海洋守護の要素を含む。
- 沼名前神社(広島県福山市)
- 『古事記』には記述がないが、伝承として綿津見命を祀り、海の航路の安全を願ったことが始まりとされる。
他にも「和多都美神社(長崎県対馬)」のように、「和多都美=ワタツミ」の名前を冠した神社が存在します。多くが漁港や島など海に近い場所に鎮座しており、漁業や航海、海運の守護を期待する地域住民の信仰が篤いです。
日本 神話 海 の 神|ワタツミや海の女神を知ろう!まとめ
1. 日本神話で海の神様は誰か?メインはワタツミ(綿津見神)。スサノオや住吉三神なども海神として語られる。
2. 海の女神は豊玉毘 海神の娘として登場する豊玉毘売が代表的な海の女神。ほかに弁財天が水神として崇敬される例も。
3. 海の神三神・わたつみ三神「底津・中津・上津ワタツミ」の三神が、イザナギの禊ぎから生まれたとされ、各海域を守護する神と伝えられる。
4. 海の神様 神社 住吉大社や宗像大社など、海洋守護・航海安全に功徳がある神社が多く、地名に「和多都美」のつく神社も全国に散在。
5. おみくじとの結び付き 海の神社でおみくじを引くなら、航海安全や漁業繁盛、あるいは人生航路の安全祈願などを願ってみるとよいでしょう。おみくじの文面が“流れに乗るが吉”と出れば、海の神の後押しを感じるかもしれません。
日本神話に登場する海の神様・ワタツミとは?総括
- 日本神話の海神は「ワタツミ」が中心
→ 「海そのもの」を指す言葉でもあり、海の支配者としての神名でもある。 - 海の女神は豊玉毘売が有名
→ 山幸彦との縁組みで、皇室の伝承にも繋がる重要な役割を果たす。 - 海の神三神
→ 三柱のワタツミや住吉大神など、文献や説ごとに異なるが、いずれも海域の安全や豊漁を司る。 - 海の神を祀る神社
→ 海辺や港町に多く、漁師や船乗り、海運業者が昔から信仰。おみくじも当然あり、海運(航運)=行い運と絡めて開運祈願する人も。
これらを踏まえ、「日本 神話 海 の 神」に興味を持ったら、まずはワタツミを祀る神社へ参拝してみましょう。海への感謝と畏敬が深まるはずです。そして、おみくじブログに書くなら、海神の歴史や信仰、神社の雰囲気などをレポートしてみると、読者も楽しめる記事になるでしょう。
神社本庁「海の守り神を祀る神社」👉海の安全を祈る神社と神道の考え方は、神社本庁の公式情報から学ぶことができます。
文化庁「日本人の宗教観と自然信仰」👉日本人の自然信仰や海の神への信仰の背景については、文化庁の宗教文化に関する資料が参考になります.