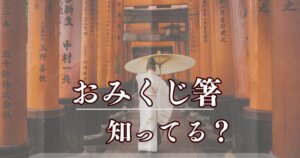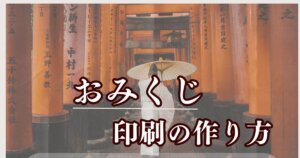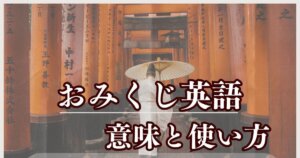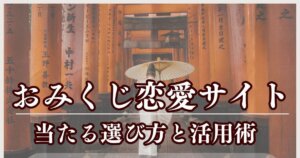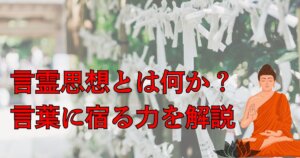「日本 神話 火 の 神」というと、多くの人が思い浮かべるのは「カグツチ(迦具土神/火之迦具土神)」ではないでしょうか。
ですが、日本神話の中にはこのカグツチ以外にも、火や炎に関係する神様が何柱か登場し、古来より生活や信仰に深く根ざしてきました。
本記事では、「日本の火神」の正体や、日本神話で描かれる火の神様たちのエピソード、さらには火の神を祀る神社や、そのご利益などについて詳しく解説します。
途中でおみくじとの関連にも触れながら、読者が抱きがちな疑問をひとつずつ解決していきましょう。
日本神話 火の神様は誰ですか?
まず最初に「日本の火の神様といえばどなたか?」という素朴な疑問に答えます。
結論:日本神話を語る際、最も有名な火の神は「カグツチ(迦具土神)」です。
ただし、厳密に言えば「カグツチ」という名称だけでなく、ホムスビ(火産霊神/ほむすびのかみ)と呼ばれるケースもあり、文献によっては表記や名前が異なります。
火の神様は複数存在する?
実は「日本神話 火 の 神」と言っても、カグツチが唯一の火神というわけではありません。例えば次のように複数の名で呼ばれたり、火に関連する役割を持つ神が存在します。
- カグツチ(迦具土神、火之迦具土神、軻遇突智など表記多数)
- イザナミが最後に産んだ火神とされ、母を焼死させてしまうほどの強烈な炎を持つ。
- 火之炫毘古神(ひのかがびこのかみ)、火之夜芸速男神(ひのやぎはやおのかみ)
- カグツチの異名/別名と位置づけられている。
- 火之御子神(ほのみこのかみ)
- 地域によっては火の御子神として祀られる場合もある。
これらは多くの場合「カグツチ」のバリエーション、もしくは関連神とされ、日本において最も代表的な“火神”のイメージを形成しています。
「日本の火の神様は誰ですか?」と問われるなら、まずカグツチの名が挙がる、というわけです。
日本神話における火神は誰ですか?
上記とほぼ同様の問いですが、「日本神話における火神」を改めて整理すると、最有力は「カグツチ(火之迦具土神)」となります。
「イザナミが産んだ火の神は誰ですか?という疑問にも直結するため、次の見出しで詳細を解説しましょう。
日本神話(特に『古事記』・『日本書紀』)で語られる「神生み」の最後に登場するのが、この火神カグツチです。
イザナミ・イザナギの夫婦神が数多くの神々を生んだ締めくくりとして、「火の神」を生んだら母親(イザナミ)が陰部を焼かれて亡くなってしまい、父親(イザナギ)は怒ってカグツチを斬り殺す、というショッキングなエピソードが有名です。
日本の火の女神は?
では、「日本の火の女神」となると、あまり耳慣れないかもしれません。
一般的な火の神としては、カグツチのような男神が広く認知されています。一方、「火の女神」と呼ばれる存在もいくつか説がありますが、実は日本神話にはっきりした女性火神が大々的に描かれているわけではありません。
ただし、火と関連のある女性神として、例えば以下が挙げられることがあります。
- カグツチの母イザナミ
- 火の神を産んで亡くなったエピソードから、火に強い関係を持つ。ただし「火の女神」と呼ぶのはやや違和感が残る
- アタゴ三女神
- 京都・愛宕神社などで祀られる火防護の神々の中に、女性神が含まれる説がある
- 火牟須比売神(ほむすびめのかみ)
- 火産霊神(ホムスビのかみ)の女性形として語られる場合もあるが、根拠は薄い
まとめると、「日本の火の女神は誰ですか?」と言われたとき、はっきり「この女神!」と同定される神は見当たらないのが現状です。
学者によっては「イザナミも火の要素を持つ女神」と見なす場合もありますが、これが“日本の火の女神”として定着しているわけではありません。
イザナミが産んだ火の神は誰ですか?
ここに至って最も直接的な質問となります。答えは「カグツチ(火之迦具土神)」です。
『古事記』では「火之炫毘古神(ひのかがびこのかみ)」「火之夜芸速男神(ひのやぎはやおのかみ)」など複数の異名が記されるほか、『日本書紀』の一書では「軻遇突智(かぐつち)」とか「火産霊神(ほむすびのかみ)」とも呼ばれたりします。
いずれにせよ、イザナミが最後に産んだ火の神といえば、カグツチを指し示します。
イザナミは、この火神の強烈な炎によって陰部を焼かれ、これが原因で亡くなって黄泉国へ赴くことになります。
この一連のエピソードが「神話の流れを次なる黄泉国訪問譚(よみのくに)につなげる」という、大きな転換点になっています。
日本神話の中でも特にドラマチックで悲壮感漂う場面として有名です。
火の神様 一覧
「日本 神話 火 の 神」を語る際、火神一覧をざっと整理しておくと便利です。多くがカグツチ周辺の名前ですが、文献や地域によって表記のブレがあるためまとめておきましょう。
- 火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)
- 別名:カグツチ、軻遇突智、火産霊神など。最も代表的な日本神話の火神
- 火之炫毘古神(ひのかがびこのかみ)/火之夜芸速男神(ひのやぎはやおのかみ)
- 『古事記』におけるカグツチの別名
- 火雷神(ほのいかづちのかみ)
- カグツチが斬られた際の血から生まれた一柱として挙がる場合もあるが、直接「火を扱う」神としてメジャーではない
- 愛宕(あたご)三神
- 厳密には「火神そのもの」というより「火難除け」の神々。男神・女神含めて諸説あり
他にも、地域の民間信仰で「火の神様」と呼ばれている神々がいますが、古事記・日本書紀に公式に載っている火の神としては、やはりカグツチが中心です。
日本神話 火の神様の神社
日本各地には「火伏(ひぶせ)の神」「火防(ひぶせ)神社」など、火災よけのために火の神を祀る神社が数多く存在します。その中にはカグツチや愛宕神社のように、火を司る神を主祭神に据えたところも多いです。
- 愛宕神社(京都府など全国に分布)
- 火之迦具土神を含む火の神々を祀るとされ、とくに京都の愛宕神社は「火伏せの神」として有名
- 秋葉神社(静岡県)
- 主祭神はカグツチではなく、別の火関連神が祀られるケースもあるが、「火防」のご利益あり
- カグツチ神社(数は少ない)
- 兵庫県西宮市の「越木岩神社」に末社として火之迦具土神が祀られている、など地域ごとに分散している
火の神様 名前 日本という切り口で調べると、「カグツチ/愛宕/秋葉/荒神(荒神社)」などがヒットし、火防信仰が日本でどれほど大切にされてきたかが分かります。
かつての日本の住居は木造が主流で火災リスクが高かったこともあり、火を鎮めてくれる「火神」の存在は非常に重要でした。
火の神 最強
「火の神 最強」という少しマンガ的なフレーズですが、日本神話において最強クラスの火神を挙げるなら、やはりカグツチが筆頭候補です。
なぜなら、その誕生の炎が母イザナミを焼き殺してしまうほど強烈で、結果的に父イザナギが怒り、十拳剣でカグツチを斬り殺す展開に至ります。
その衝撃が、日本神話内でも屈指の“壮絶なシーン”とされることから、「火の神 最強」と言えばまずカグツチでしょう。
もっとも、神話世界は「最強かどうか」で単純に序列化できるものではなく、それぞれの神に役割があり、“強さ”は状況によるともいえますが、カグツチの火力は別格と言えるでしょう。
火之迦具土神 ご利益
火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)は、母を焼き殺してしまうほどの強烈な火力を持つ存在ですが、信仰の面では単なる“恐ろしい火神”ではありません。ご利益としては、主に次のようなものが挙げられます。
- 火防護・火伏(かぶせ)
- 火事から守ってくれる。大火や家事を避け、家庭の安全を守る。
- 鍛冶・金属精錬の守護
- 火を扱う職業(焼き物、鋳物、鍛冶など)にとって、火神は生業(なりわい)の守り神。
- 生活全般の安定
- “火”はかまどを象徴し、家族の食事や暖房に不可欠なため、家内安全や繁栄の象徴ともなり得る。
とくに、焼き物や鍛冶を営む職人が火之迦具土神を深く崇敬してきたという歴史はさまざまな史料に残っています。木造住宅の多い日本では、火災は大きな脅威だったため、「最強の火神」であるからこそ、しっかり祀って火難除けを願うという心理が働いたのでしょう。
火之迦具土神 神社
火之迦具土神(カグツチ)を主祭神として祀る神社は数は多くありませんが、全国に点在しています。メジャーな例として:
- 愛宕神社(京都市)
- 正式には火之迦具土神のみを主祭神としているわけではありませんが、火伏の神として知られ、カグツチを含む火の神々を総合的に祀っているとされる。
- 秋葉神社(静岡県)
- 秋葉三尺坊大権現やその他火防神とセットで祀られる場合がある。地域差あり。
- 越木岩神社(兵庫県西宮市)末社
- 火之迦具土神が末社として鎮座していることで知られる。
- 各地の「火之迦具土神社」「加具土命神社」
- ただし知名度は高くないため、ローカルな氏子エリアで祀られる程度。社名から検索すればいくつかヒットします。
火之迦具土神を祀る神社では、おみくじや御朱印ももちろんありますので、神社巡りの際はこうした“火神”を祀る社を訪ね、おみくじを引いて“火難除け”や“家内安全”を願うのも面白いでしょう。
おみくじブログに投稿する場合でも、「火の神様」に関連するご利益を紹介する形で、読者の関心を引けるはずです。
火産霊神 カグツチ
「火産霊神(ほむすびのかみ)」は、別称あるいは別表記としてのカグツチの呼び名です。
「産霊(むすひ)」という言葉には、“新たな命や力を生み出す”という積極的・生成的な意味合いがあります。火というと怖いイメージですが、一方で火があるからこそ調理ができ、鉄を精錬でき、暖をとれるという正の面があるわけです。
- 火=破壊と創造を同時に担う
- 伊邪那美を焼き殺すほどの破壊力がありながら、一方では金属精錬や焼き物などの生産を支える創造力でもある。
- ムスビの神々
- 日本神話には、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)や神産巣日神(かみむすびのかみ)など、“むすび”を名にもつ神が複数います。火産霊神もそうした“ムスビ”系の一柱とされる場合があり、火を媒介として新たな恵みをもたらす性格を帯びています。
神殺しカグツチとは?
神殺しカグツチとは?(迦具土神)火を管理する神様=火産巣日神(ほむすびのかみ)
最後に、カグツチには「神殺しに遭った神」というイメージがあります。
実際、カグツチは“母を死に追いやった”という事実に怒った父・イザナギによって、抜き身の十拳剣で斬り殺されてしまいます。神殺しカグツチ という言い方は、創作物などで「カグツチが殺された神である」あるいは「カグツチ自体が他神を焼く力を持つ凶暴な存在」として描かれる場合に使われる表現です。
いずれにせよ、カグツチ(迦具土神)=火の管理を司る神様として理解しておくと、日本の火の神に関する概念をつかみやすいでしょう。
- 火を管理する神様=人間社会に火を提供し、同時に火災を制御する役目
- 破壊と創造の両面を持つからこそ、産霊(むすび)の要素が取り込まれている
日本では古来、神社での祭祀や日常生活の中でも火の扱いは非常に神聖視されてきました。たとえば祭りや儀式で「忌火(いみび)」を用いたり、かまど神を祀ったり、正月には歳神を迎える“とそ火”があったりと、火は常に神聖な力を象徴してきたのです。
カグツチを中心に「日本 神話 火 の 神」を知ると、それがいかに大事な概念かがよくわかります。
おみくじと火の神様の関係は?
- 火の神は開運の象徴にもなる
- 火をうまく使えば食事や暖房など生活を豊かにする。おみくじの“末吉”“吉”と同様、使い方次第で吉凶が変わる。
- 火伏せ・火難除けのお守り
- 火の神を祀る神社で引くおみくじは、火災除けや厄除け、繁盛の暗示が出る場合があり、参拝との相乗効果が期待できる。
- イザナギ・イザナミのドラマに学ぶ
- 神話を知ると、おみくじで“努力すれば吉”と出ても、やりすぎるとイザナミのように痛い目を見るという反面教師にもなる。
神社でおみくじを引く際は、火神を祀っているところか、火難除けにご利益のあるところを探してみるのも一興です。自宅や店舗を火災から守りたい人にとって、「火防(ひぶせ)の神」としてのカグツチ信仰は今なお人気があります。
結論・火の神様のまとめ|日本 神話 火 の 神
- 日本神話の代表的火神は「カグツチ(迦具土神/火之迦具土神)」
- イザナミが産んだ直後に母を焼き殺すほどの力があり、イザナギに斬られる
- 火神一覧では、カグツチの異名や火防を司る神々(愛宕神など)も含む
- ご利益は火難除け・家内安全・鍛冶や焼き物など火を活用する職業守護
- 火の女神という明確な存在は日本神話には乏しいが、イザナミが火を生んだ母として重要
- カグツチの神社は数多くないものの、火鎮(ひしずめ)祈願で崇敬される例が多い
- おみくじブログに絡めるなら、火の神様を祀る神社での参拝記や火難除けの話題が面白い
以上のように、「日本 神話 火 の 神」はカグツチを中心に、イザナミ・イザナギの神生み神話、さらに火難除けや職人の火利用との深い関わりが見えてきます。
もし火の神社を訪れておみくじを引くなら、「火」を連想させるような結果(例:一気呵成に進めば吉、あるいはやりすぎると凶など)が出た時に、神話を思い出してみるのも良いかもしれません。火は私たちの生活に不可欠な力ですが、使い方を誤れば大惨事になる危うさもある――日本神話はこの両面を強烈に伝えているのです。